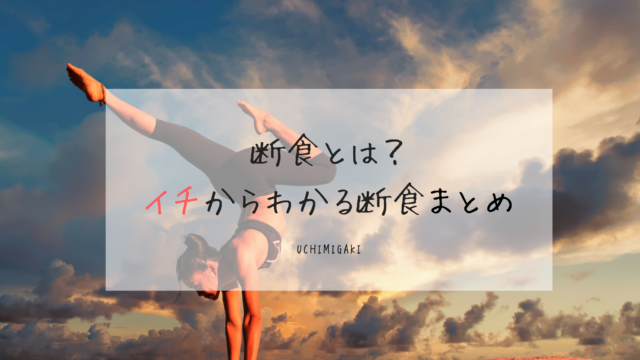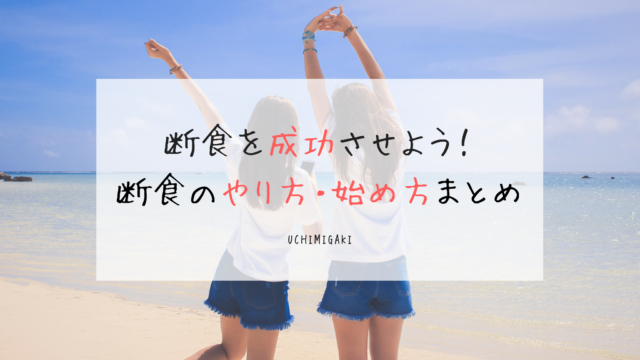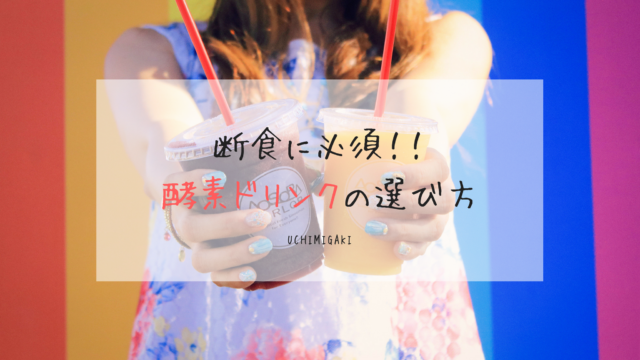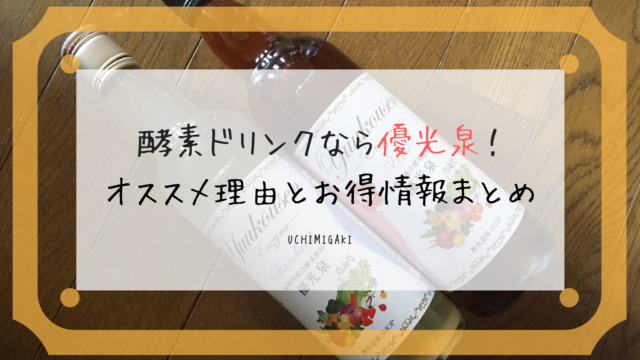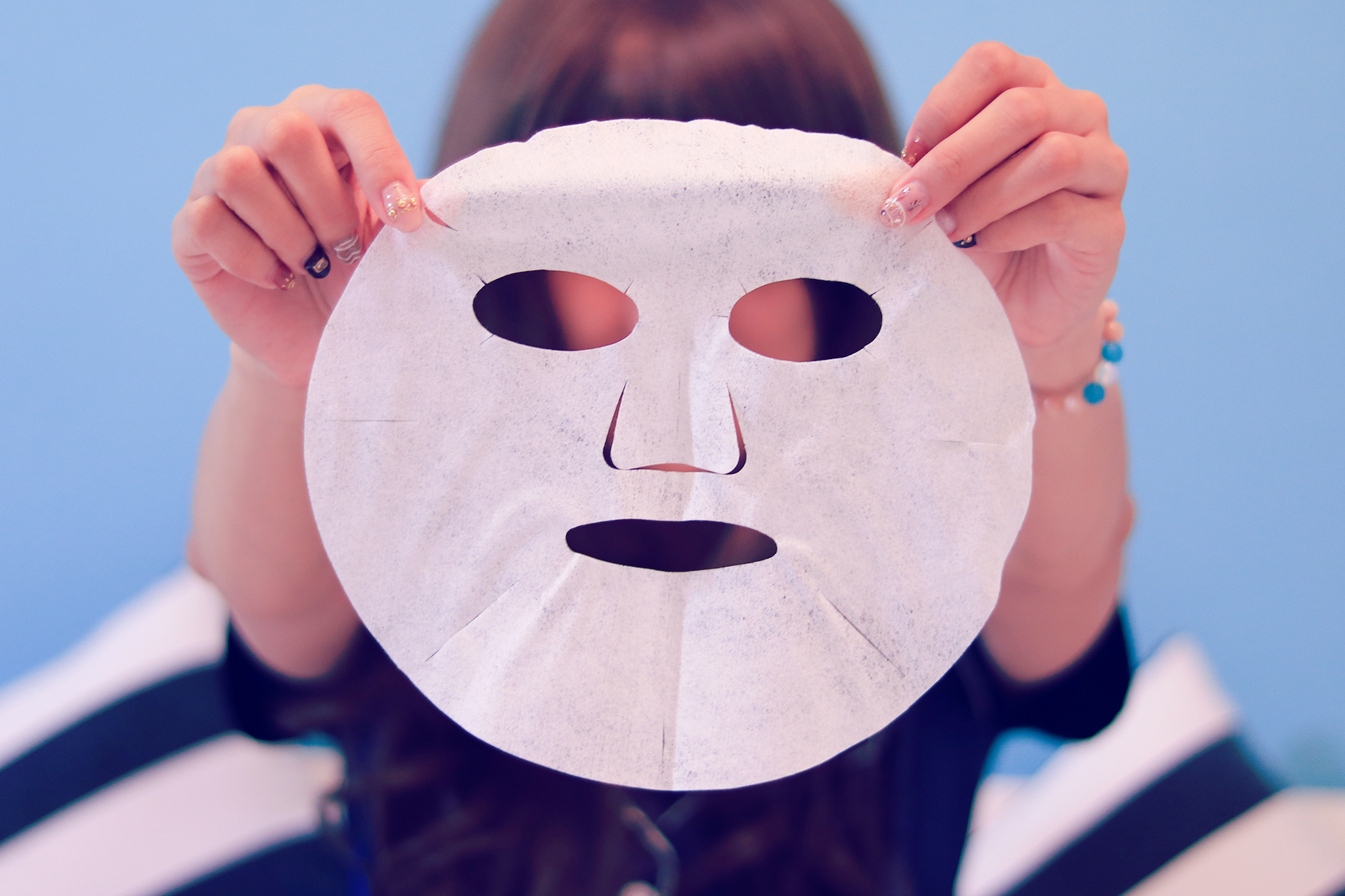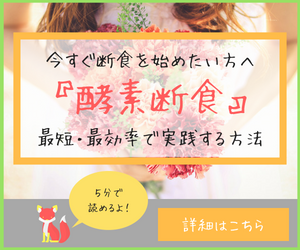こんにちは、ミカです!
今回は酵素と並んでよく登場する『補酵素』について詳しく解説していきます!
そもそも酵素って何?というあなたはこちらからまず読んでね!
[st-card id=835]
補酵素とは

補酵素の語源
『補酵素』とは、英語でcoenzyme(co=補う、enzyme=酵素)と書きます。読み方はコエンザイム、これどこかで聞いたことありませんか?
[st-kaiwa3]あ!コエンザイムQ10!![/st-kaiwa3]
よくCMやサプリなんかで一躍有名になったビタミン様化合物の一種ですね!実は、コエンザイムQ10はビタミン様化合物の一種であると同時に、補酵素の一種でもあるのです。
補酵素と酵素の関わり
酵素はタンパク質の一種ですが、構造によって大きく2種類に分けられます。一つはタンパク質のみで構成されている酵素(アポ酵素)、そしてもう一つはビタミンやミネラルを中心にタンパク質が巻きついた構造をしている酵素(ホロ酵素)です。体内にいる酵素は潜在酵素と呼ばれていますが、その潜在酵素は人間の生命維持活動すべてに関わっています。そして、潜在酵素の多くがホロ酵素であり、アポ酵素の状態である酵素はうまく潜在酵素として機能しません。(もちろんアポ酵素でも機能しているものもあります)
そこで、アポ酵素はホロ酵素になりたいと、『ホロ酵素にあって自分にないもの=足りないもの』を求め、ビタミン・ミネラルを手に入れようとします。ゆえに、酵素の足りない部分であるビタミン・ミネラルの多くは、酵素のサポーターということで『補酵素』と呼ばれるようになりました。
補酵素と酵素は互いに助け合っている
アポ酵素がホロ酵素にならないと活躍できないものがいることと同様に、補酵素であるビタミン・ミネラルの中にも酵素なしには体内で活躍できないものもあります。ですので、酵素の元となるタンパク質だけを摂取しても意味はありませんし、補酵素であるビタミン・ミネラルのみを体内に摂取しても効果が見られない可能性が高いです。
[st-kaiwa1]私も昔馬鹿ほどビタミン・ミネラル関連のサプリを飲んでましたけど、効果は全然感じませんでした。摂るタイミングも量も適当でしたから・・・。[/st-kaiwa1]
なので、もし体内酵素のためにといって補酵素サプリを摂取するのであれば、そのタイミングはとても大切になってきます。
補酵素サプリの効果的な補い方
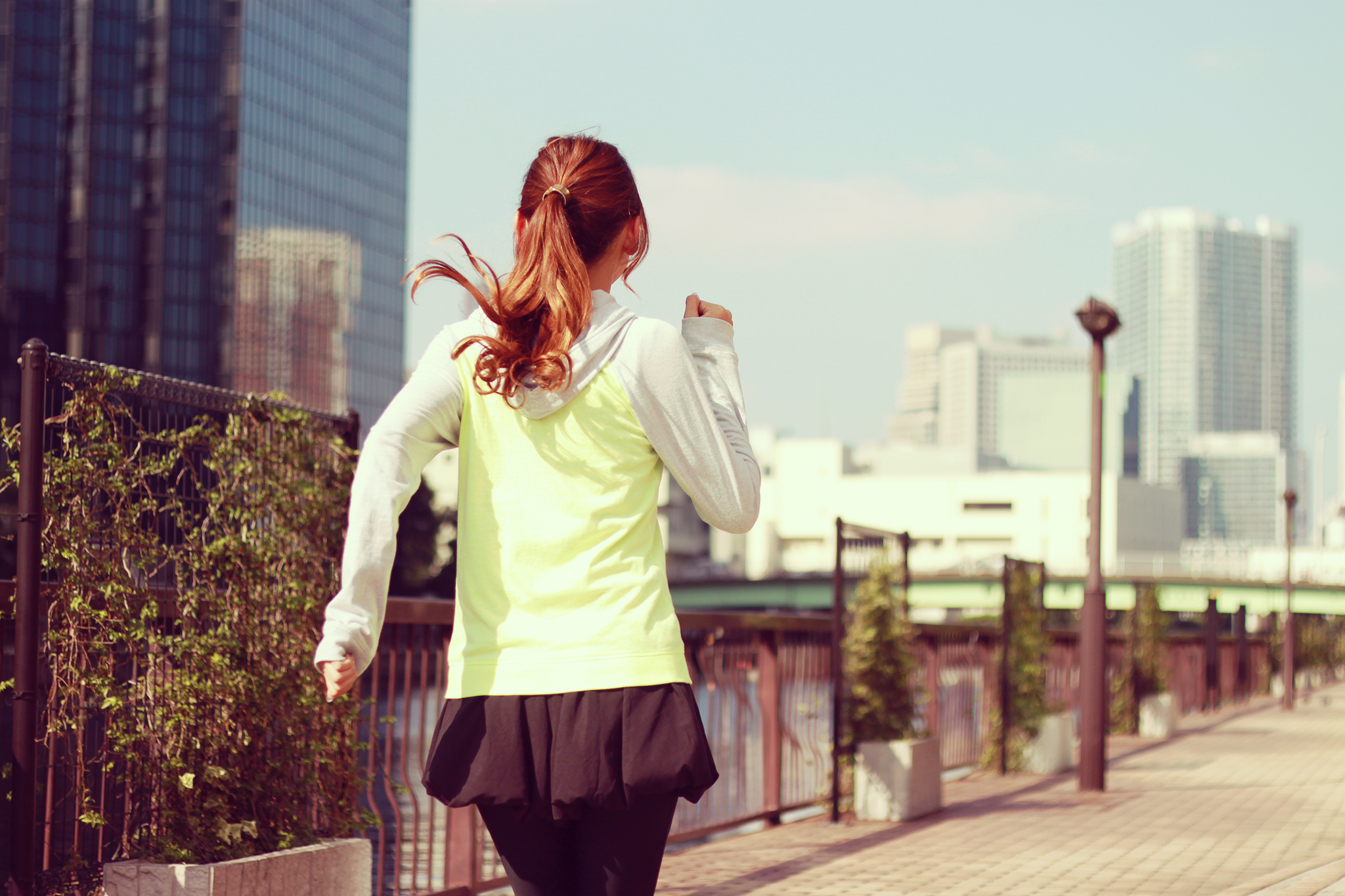
タンパク質と一緒に摂取!
補酵素の相方である酵素はタンパク質からできています。それに加えて、体内酵素は体外から摂取することができません。なので、酵素の材料であるタンパク質を体内に補うことで、体内酵素の生成をサポートします。
というわけで、補酵素であるビタミン・ミネラルもタンパク質を補うタイミングで同時に補給すると良いでしょう。
しかしながら、食物とはなんと素晴らしいことか。基本的にタンパク質の塊である肉・魚・大豆などは皆ビタミンB群を多く含んでいます。あとで解説はしますが、このビタミンB群というものがまさに『補酵素』の一種でもあります。つまり、肉・魚・大豆などを食べるだけで酵素の材料は完璧といえるわけです。
というわけで、肉・魚・大豆などをしっかり食べましょう!
酵素の多い食物と一緒に摂取!
酵素は生野菜や果物などの生ものに多く含まれており、それらをすりおろしたり細くすることで繊維質が切れて酵素がはじけ出ます(酵素が多くなるということです)。また、ドライフルーツやナッツ、海藻、海苔、天日干しした野菜、発酵食品などにも酵素は豊富に含まれています。
しかしながら、先ほども言いましたが、体内酵素は体外から摂取することができません。仮に体外から酵素が入ったとして、それらは体内酵素によって分解吸収されてしまいます。ですが、だからと言って体外から酵素を補給することに意味がないとは言えません。酵素はタンパク質なのですから、体外から酵素を補給するということはタンパク質を補給するということ。つまり、酵素の多い食物は肉・魚・大豆以外でも良質なタンパク質を補うことができる手段として効果的です。
そこで、私が補酵素補給に提案するのが、酵素の多い食物との同時摂取です。生野菜や果物などの酵素の多い食物には良質な酵素(タンパク質)が豊富ですから、そこに肉・魚・大豆に多く含まれるビタミンB群などの補酵素を加えることで、体内酵素の生成キットの出来上がりというわけです。
というわけで、補酵素のサプリを摂るならば、酵素の多い食物と一緒に摂取しましょう!
補酵素の種類と多く含む食品をご紹介
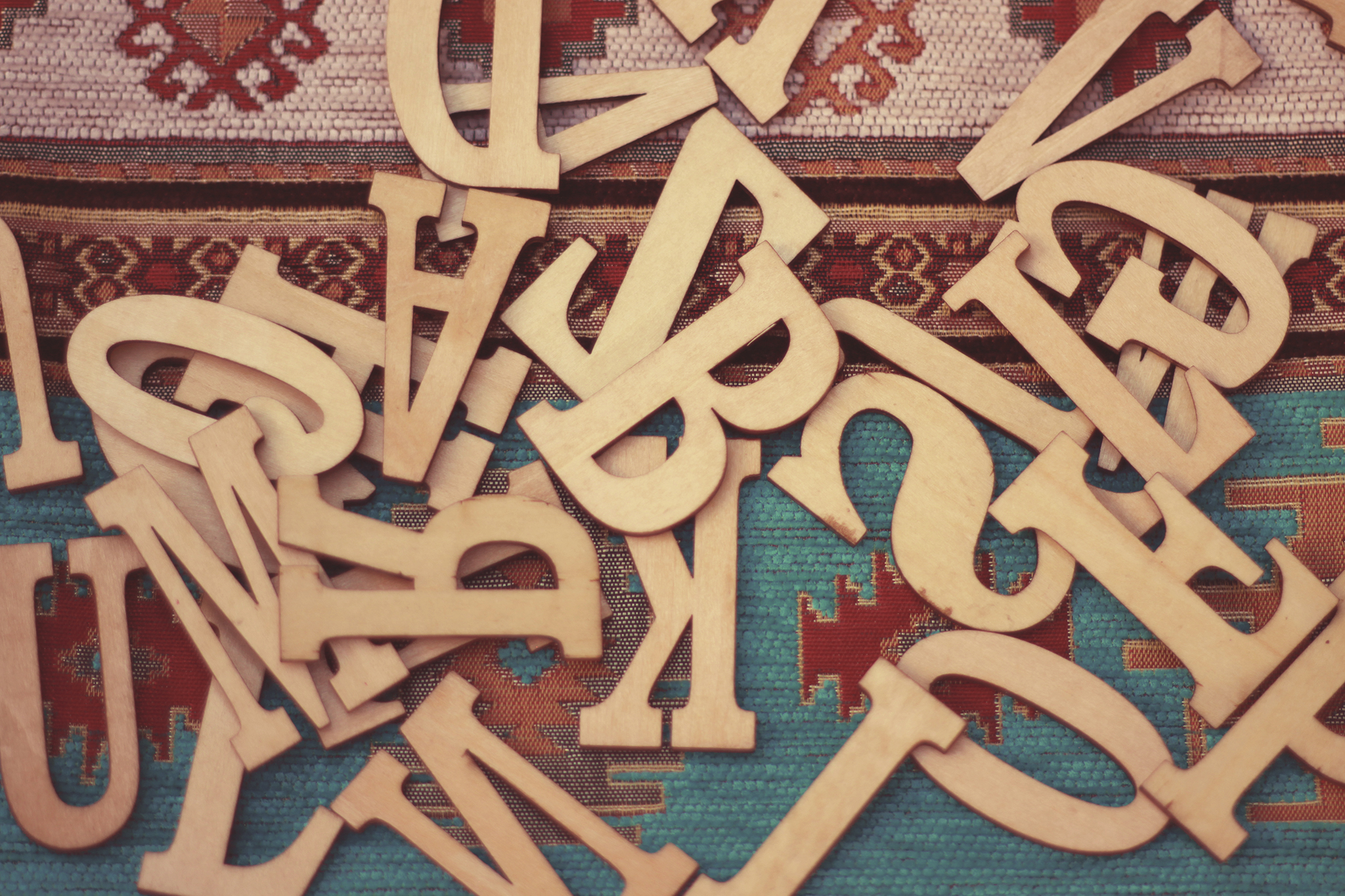
ここでは、先ほど補酵素として紹介したビタミンB群を含め、ほんの一部ではありますが、補酵素の代表選手である3種類のビタミン・ミネラルなどを紹介します。
多く含まれる食材も一緒に紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
補酵素ビタミン代表!ビタミンB群
| ビタミンB群 | 補酵素としての役割 | 多く含まれている食材 |
| ビタミンB1 | 糖質・アルコールをエネルギーに変える | 豚ヒレ肉、うなぎ、玄米ご飯、ナッツ、たらこ(全て、煮る・蒸すがおすすめ) |
| ビタミンB2 | 脂質をエネルギーに変える | 豚レバー、納豆、うなぎ、牛乳 |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 糖質・脂質の分解に必要 | カツオ、豚レバー、ピーナッツ、たらこ |
| ビタミンB5(パントテン酸) | 糖質・脂質・タンパク質の代謝に必要 | レバー類、鶏もも肉、ニジマス、納豆 |
| ビタミンB6 | タンパク質の分解・再合成に必要/脂質の抗酸化 | マグロ、牛レバー、さんま、カツオ、バナナ |
| ビタミンB7(ビオチン) | 皮膚の健康を保つ | レバー類、イワシ、落花生、卵、ニシン |
| ビタミンB9(葉酸) | 細胞分裂に必要/ビタミンB12とお友達 | 鶏レバー、菜の花、枝豆、ほうれん草、からし菜 |
| ビタミンB12 | 造血に必要/葉酸とお友達 | 牛レバー、鶏レバー、牡蠣、さんま、あさり、ニシン |
ビタミンB群は、その種類によって様々な働きかけを行っています。中には、ビタミンB9(葉酸)のようにビタミンB12と一緒になることで互いに働きやすくなるものもいます(ビタミンB2とB6、ビタミンB群と核酸*¹もそうです)。なので、ビタミンB群を摂取する際は、ビタミンB1単体で摂るなどというよりも、ビタミンB群全体として複合体で摂取することが望ましいです。
*¹:核酸とは、日々生まれ変わる新しい細胞の生成に必要な物質で、ビタミンB群が人体で働けるようになるために必須の栄養素です。
補酵素ビタミン風代表!コエンザイムQ10(CoQ10)
コエンザイムQ10(CoQ10)は、かつてビタミンQと呼ばれていたビタミン様化合物(ビタミンではない)*²のことであり、人体の中でのエネルギー作りやサビ取り(抗酸化作用)を行う大切な栄養素です。学名では「ユビキノン」とも呼ばれています。
*²:ビタミンの定義は「微量で体内の代謝に重要な働きをしているにもかかわらず、自分で作ることができない化合物」です。コエンザイムQ10は、ビタミンのような働きをするが、体内で生成できるため『ビタミンではない』、つまり、ビタミン様化合物に分類されるというわけです。
コエンザイムQ10の役割は、コエンザイム(補酵素)として体内の筋肉を動かすエネルギーであるATP(アデノシン三リン酸)の生産と、サビ取り(抗酸化)です。
この2つはどちらも人体活動になくてはならない要素であり、もしコエンザイムQ10が不足するようなことがあれば、細胞内でのエネルギー作りが滞ったり、体内が錆び付いていくことにつながります。それはつまり、私たち人間の筋力の低下や体の衰えに直結してくるということです。また、コエンザイムQ10は体内で生成できるのですが、加齢とともにその生成量は減少していきます。ですので、私たちは体外からコエンザイムQ10の多い食材やサプリなどを補給する必要があります。
コエンザイムQ10の多い代表的な食材としては、『大豆・くるみ・アーモンド・ほうれん草・青背魚(イワシなど)』があります。
しかしながら、コエンザイムQ10を体内で十分に効果を発揮させるためには、いくら多い食材といえども、とても食べきれないほどの大量の食材を食べなければならないとのこと。ですので、コエンザイムQ10に関しては、サプリメントで補給することが望ましいです。
補酵素ミネラル代表!金属イオン
補酵素として働くものはビタミンだけではありません。ミネラルである金属イオンも補酵素として関わっています。そこで補酵素として働く重要なミネラル類を表にまとめました。各種内容を参考に上手に摂取してくださいね!
| 金属イオン | 補酵素としての役割 | 多く含まれている食材 |
| マグネシウム | 筋肉の弛緩作用や神経伝達作用などのATPに関わる酵素反応に必要 | 青のり、干しエビ、ゴマ、きな粉、落花生、玄米、納豆 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成・分解に関与/抗酸化酵素SOD*¹の合成に必要/過剰摂取で鉄と銅の吸収阻害 | 牡蠣、パルメザンチーズ、豚レバー、抹茶、たたみいわし、ゴマ(全て、動物性たんぱく質と同時摂取で吸収率アップ) |
| 銅 | 抗酸化酵素SOD*¹の合成に必要/鉄とお友達 | 牛レバー、ホタルイカ、フォアグラ(茹で)、ゴマ、あんこうの肝、豚レバー、大豆、ココア |
| マンガン | 糖質・タンパク質・脂質の代謝を活性化/糖新生*²・抗酸化酵素SOD*¹の合成に必要 | 青のり、キクラゲ、黒胡椒、生姜、玉露、くるみ |
| セレン | 抗酸化酵素の活性化・有害物の無毒化に関与 | カツオ、イワシ、ホタテ、牡蠣、玄米 |
| クロム | 糖質・脂質代謝を活性化に関与 | 海藻類、魚介類、レバー類、豆類、キノコ類、未精製の穀物、ビール酵母 |
| モリブテン | 核酸・糖質・脂質の代謝や貧血予防、有害物の体外排出に関与/過剰摂取で銅の排出 | きな粉、大豆、落花生、枝豆、玄米 |
*¹:SODとは、Superoxide dismutase(スーパーオキサイドディスムターゼ)の頭文字として表記される活性酸素除去酵素のこと。
*²:糖新生とは、血中のブドウ糖量が低下した時に、肝臓でブドウ糖を生成する仕組みのこと。
他、ミネラルについてはこちらの記事も参考になるかと思いますので、貼っておきますね!
[st-card id=343]
まとめ

いかがでしたでしょうか?
酵素を利用して効率よく体内環境を整えたければ、補酵素の存在は無視できませんよね。特に体内酵素は体外から摂取できませんから、なおのこと体外摂取できる補酵素のことを知るべきだと思います。巷では酵素は体外から摂取できるから酵素を補いましょうなんていう嘘八百が流れていますが、正直言って酵素を摂取することを頑張るのであれば、そのベクトルを補酵素に向けて欲しいと思います。
あなたは今この記事を読んで補酵素についての仕組みや多く含む食品などを知りました。なので、あなただけでも酵素に関しての嘘八百に騙されず、是非ともその知識を生かしてうまく補酵素を補ってくださいね。
では、今回の記事のまとめに入らさせていただきます。
- 補酵素はタンパク質のみでできているアポ酵素をホロ酵素(タンパク質+補酵素)にする働きがある。
- 潜在酵素の多くはホロ酵素であり、アポ酵素はそれ自体では機能できないものが多い。
- 補酵素は主にビタミン・ミネラルなどが当てはまる。
- 酵素は補酵素なしに機能せず、補酵素は酵素なしに機能しない。(極論)
- 補酵素を補うタイミングは、タンパク質や酵素の多い食物など酵素の元となるものと一緒がベスト。
- 補酵素代表選手は、ビタミンB群・コエンザイムQ10・金属イオン
以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました!
補酵素の摂取は『日本人の食事摂取基準』を守り、正しく摂取してくださいね!

断食を成功させたいなら、酵素ドリンクは必須です。
中でも私がオススメしたい酵素ドリンクである『優光泉』は、
- 完全無添加で糖分・エキス不使用
- 原材料名は60種類の野菜等のみ
- 30日間商品返品・返金保証(開封後も返品OK)
- 断食法の指導とアドバイスを無料カウンセリング
と断食のサポートに必要なものがすべて揃っています!
断食のやり方がわからなくても付属の冊子に説明がきちんとあるので安心(びっくりするくらい中身が濃い資料になってます)。
断食初心者から玄人まで、すべての断食を行う方に手にとってもらいたい1本です!